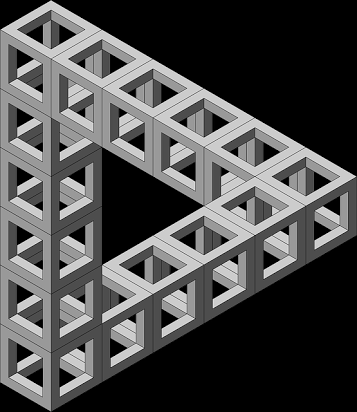時代を戻し、西暦1998年頃の話。高校野球ではレッドソックスの松坂大輔選手が大活躍し、マーク・マグワイアがシーズン70本塁打達成。サミー・ソーサも66本塁打MLBシーズン最多本塁打記録対決がテレビを独占するのかのように流れていた頃だ。
ちょうど町ではMISIAが『つつみ込むように…』でデビューし、ヒット。いたるところで流れていたのを覚えている。
当時の僕はというと、16歳で将来のはっきりしたビジョンなどなく、東京の下町蒲田にあるサーフショップで週末に連れてってもらえるサーフィンという新しい遊びを、どのようにしたら最短最速で上達できるかという問題ばかりを、来る日も来る日も天井に張ってあるシェーンドリアンのポスター向かって念仏のように質問していた。
その頃、蒲田あたりにはサーファーが沢山居て、先輩達は皆かっこよく見えて、ケンカ・女・タバコ・シボレー、というまさに「彼女の親にすれば絶対関わってはいけないタイプ」の象徴だったと思う。
そんな中、先輩の一人が学生パーティーの企画で大儲けしたのでバリ島に2カ月滞在するという。「お前も来るか?」そう言われた僕は二つ返事でそれに応えた。
簡単に行くとは行ったものの、お金は無かった。
父に貸してもらえないか相談したが、「お金なら自分で稼げるだろ」と即答。
当然だ。毎日サーフィンのポスターに念仏を唱えている奴の返済能力がどれほど低いかなど誰でも解る。
僕は10日後には先輩にチケット代を渡す約束をしていたものの、一向にお金を用意する手段が整っていなかった。
まずい、、一日15000円は稼げないと目標には達成しないだろう。その時はこのチャンスに乗り遅れるとサーフィン人生は開かれないような恐怖や危機感を抱いていたのを覚えている。当時の僕達には引越しのバイトで日給7000円の報酬を得るのがましな方だったのだ。
僕の隣の家には解体業を営むおじさんが住んでいた。僕はおじさんの犬3匹を定期的に土手に散歩に連れていく報酬として、小学生の頃から周り同級生よりも多くの収入をおじさんから得ていた。
サーフィンの事しか考えられない脳も少しは働いたようで僕はおじさんにアルバイトをさせてくれとお願いする事にした。
おじさんは、僕の相談を快く受け入れてくれた。ちょうどガラ(解体で壊したコンクリートなど)を運ぶ仕事頼んでいた中国人グループが実は不法滞在で、昨日ゲームセンターでゲームをしている時に警察に職務質問に遭い、そっくりいなくなって困っているという。僕は当時の大流行していたドコモのN形式の折りたたみ電話を素早く手に取ると、おじさんの前で意味不明に赤に点滅するアンテナを振りながら、知り合いや後輩に電話しまくった。
結局電話帳に載っている300件近くの見込みのなかから、僕を入れて9人の労働者が集まった。
皆学校に通っていたので、マッチングが難しかったが、当時16歳で1日に12500円も稼げる日当と晩御飯も保証されるというメリットは効果的だったのだ。なかには学校の制服のまま作業車に乗り込み、現場で作業着に着替えをする者もいた。
しかし僕らは、社会の洗礼を早々に受ける事になる。滑り出しは鼻息が荒かったものの、ガラの運び出しは気が遠くなるほど過酷で、まるで奴隷のようなハードな労働環境だった。
中には、労働環境の苛酷さに逃げる者もいた。翌日の集合に現れない。電話も出ない。こんな状況だ。一人減り、二人減り、最終的に残ったのは4人になった。
そんな中、一筋の光が見えた。辛い仕事の中でも、頭を使い効率化を行う事で、労力を減らしてスムーズになると思った僕はおじさんに交渉して「ウィンチ」を使う事を承諾してもらう。ウィンチとは上下のボタンがついたリモコンを操作する事でワイヤーロープを使って上層階にある簡易的な道具や荷物を下層部に移動するマシンだ。
このマシンを初期から使えなかったかは未だに謎であるが、おそらく僕らがマシンの免許を所有していなかったからだと推測している。
こうして僕らは無免許ウィンチのレバレッジを効かせて搬入作業は加速した。だが、決められた重量より上回るようなリスクのある行動は絶対にしなかった。
作業は効率的になり、当初7日かかると想定した仕事は6日で終わり迎える事ができた。
おじさんは、最後の日の夜に僕らやその他の従業員を焼き肉屋に連れて行ってくれて、僕らは盛大に盛り上がり、お互いの将来を語り明かした。
そして、帰路に着くときにおじさんが一人ずつ給料袋を渡してくれた。
僕は中身を見てびっくりした。想定よりも5万円も多いのである。
周りを見ると皆も中身の違いに動揺している様子だった。
おじさんは、「スナックでも行ってくる」と言って、さらっと部下の送迎したセンスの悪い真っ黒のベンツに乗り込んで、夜のネオン街に遊びに行ってしまった。
僕は嬉しさと、今までの努力が報われたような暖かい抱擁感のようなものに包まれた。
おじさん、ありがとう。
僕はようやくバリ島へのチケット代を手に入れた。
しかし、本当に得た物はお金やバリ島のチケットではなかった。
いまさら気付かされたが、気風の良い男の背中を見られた事だ。
仁徳のある人間は人を魅了する。お金以上に。